| |
愛知用水には 112kmの大きな(メイン)水路=「幹線水路」と
そこから枝分かれして網の目のように広がっている水路=「支線水路」
(合計約1,000km)があります。
|

分水口 |
|
「幹線水路」には
「分水口(ぶんすいこう)」というものがついていて そこから「支線水路」に水を送ります。
愛知用水には約150ヶ所の「分水口」があります。 |
|
|
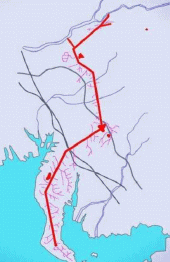
幹線水路(太い赤い線)
支線水路(細い赤い線) |
「支線水路」の末端まで水を送るにはある程度の水位がいるため
「幹線水路」の全体に一定の水位を保つよう多量の水を流し続ける必要があります。
また そこで余った水は最後には捨てることになり とっても もったいないことになります。 |
そこで
水路にゲート(門扉)をつけると・・・
(右図参照)
区間ごとに水路の水位を一定にしておくことができるのです。
このゲートを「水位調整ゲート(チェックゲート)」といいます。
(ゲートの開け閉めによって水位を調整します) |
|
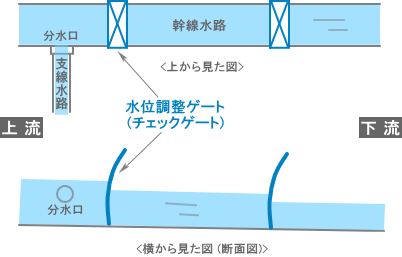 |
| 愛知用水には35ヶ所の「水位調整ゲート」かあります。ゲートにはいろいろな種類があるので紹介します! |
| <その1> 電動ラジアルゲート |
|
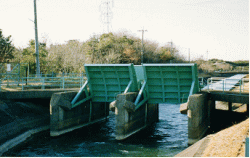 |
|
愛知用水ができたばかりの時は約半数がこのタイプ。
電気の力でゲートを開閉します。
操作は現地でおこなうので人手や時間がかかります。 |
|
| <その2> 無動力自動ゲート 『アミルゲート』 |
|

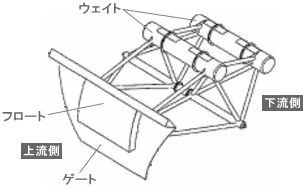
(図1) |
|
電気を使わず 流れてくる水の力のみでゲートが開閉します。
しくみは左の(図1)のようになっていて
上流側の決められた水位より上がると「フロート」と「ウェイト(おもり)」のバランスにより「ゲート」が上がり下流側に水を流します。
逆に上流側の水位が下がると「ゲート」は下がり 水をせきとめるので水位が上がります。
水位の状況に応じて勝手に(自動で)動くので人手がかかりません!
でもこのタイプは最初に決めたられた水位を変えることができません。(変えるには再び計算しなおし 設備を改造しなければなりません) |
|
|
|