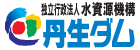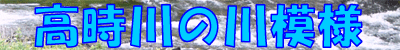高時川の川模様 〜河川巡視で出会ったもの〜
平成21年11月18日号
本日は、久々の晴天なり! 11月11日に潤いを取り戻した高時川は、水の濁りもなく清らかな流れとなっていました。
11月12日には、びわヤナ(長浜市落合町)でビワマスの産卵遡上も見られ、力強い自然の営みに心が柔らかくなりました。
上流域では紅葉も進み、間もなく見頃を迎えるのではないでしょうか。しばらくはまとまった雨の予報もありませんが、このまま瀬切れの終了となればいぃなぁと思う今日この頃です。
11月12日には、びわヤナ(長浜市落合町)でビワマスの産卵遡上も見られ、力強い自然の営みに心が柔らかくなりました。
上流域では紅葉も進み、間もなく見頃を迎えるのではないでしょうか。しばらくはまとまった雨の予報もありませんが、このまま瀬切れの終了となればいぃなぁと思う今日この頃です。
平成21年11月16日(月)の状況
 阿弥陀橋上流 |
 福橋上流 |
 びわヤナ |
平成21年11月18日(水)の状況
 阿弥陀橋上流 |
 福橋上流 |
 びわヤナ |
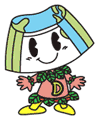
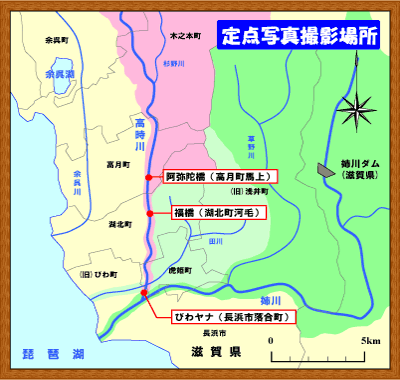

河川巡視等で職員が現場に出かけた際には、自らが気がづいた様々な状況も撮影しています。これらの記録は、移りゆく周辺環境を把握し、それらの情報を有効活用していくためのものでもあります。
【11月16日】井明神橋のたもとでは、メスのビワマスが、卵を産み付けるための産卵床を掘っていました(写真-1)。後ろにくっついているのがオスですが、魚の世界も「母は強し!」なんでしょうか?
【11月18日】高時川のすぐ近くに、国宝十一面観音像で有名な向源寺があります(写真-2)。境内の木々もほどよく色づき、参拝の方々で賑わっていました。いぃお天気でよかったですね。
【11月18日】湖北野鳥センターの目の前の琵琶湖は、たくさんの水鳥たちが飛来しています(写真-3)。風がすごく強かったからなのか、水鳥たちはみんなおとなしくたたずんでました。寒いと言う訳じゃないと思うんですけど・・・。
【11月18日】高時川のすぐ近くに、国宝十一面観音像で有名な向源寺があります(写真-2)。境内の木々もほどよく色づき、参拝の方々で賑わっていました。いぃお天気でよかったですね。
【11月18日】湖北野鳥センターの目の前の琵琶湖は、たくさんの水鳥たちが飛来しています(写真-3)。風がすごく強かったからなのか、水鳥たちはみんなおとなしくたたずんでました。寒いと言う訳じゃないと思うんですけど・・・。
 写真-1 ビワマスの産卵行動 (木之本町石道 H21.11.16) |
 写真-2 向源寺 (高月町渡岸寺 H21.11.18) |
 写真-3 湖上の水鳥たち (湖北町今西地先 H21.11.18) |
高時川の中下流部では、水面がなくなり川が干上がる「瀬切れ」という現象が毎年のように発生しています。瀬切れの結果、遡上したアユなどが大量に死んでしまうとともに、周辺では死んだ魚による強烈な悪臭被害も発生しています。
また、高時川下流域は昔から地下水に恵まれた地域で、水道用水などの水源として年間1.5〜2.5億m3が利用されてきました。しかし、近年、一部の地下水位は低下傾向にあり、安定的な地下水利用に対する不安があります。
また、高時川下流域は昔から地下水に恵まれた地域で、水道用水などの水源として年間1.5〜2.5億m3が利用されてきました。しかし、近年、一部の地下水位は低下傾向にあり、安定的な地下水利用に対する不安があります。
高時川の瀬切れ発生状況【平成21年11月18日現在】
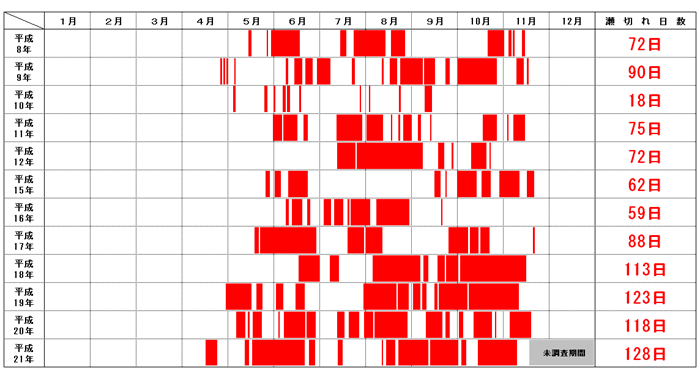
注1)平成13年と平成14年は調査を行っていません。
注2)平成21年の結果は速報です。
注2)平成21年の結果は速報です。