| 下久保ダムの情報
> キッズコーナー入口>
水と川とダムのおはなし【5/7ページ】 |
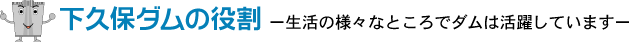 |
 |
 |
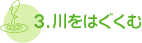 |
 |
| 安定して水が利用できるようダムに水を貯えて、みんなの暮らしに必要なだけ、安全に供給します。 |
台風などで降る大雨をダムに貯めることによって、一度にたくさんの水が流れるのを防ぎます。 |
ダムから流す水の量を調整し、川やその周りに生息する生き物などを護り、川の役割を損なわないよう、一年を通して安定した水量を保ちます。 |
ダムから放流する水を利用して電気を生み出し、みんなの家に送られます。 |
「水争い」とは、水不足の時に少ない川の水を巡って農業用水を奪い合う争いのことです。特に新田の開墾が進んだ江戸時代からは、全国各地で見られるようになりました。
江戸時代の神流川には8つの農業用取水堰があり、川の上流からそれぞれ「九郷用水堀口分」「牛田堰」「安保堰」「肥土村用水」「根岸堰」「戸塚堰」「五明堰」「勅使河原堰」と呼ばれていました。
川の上流にある取水堰が川の水を全て取ってしまっては、その下流に水が行き渡らないので、江戸幕府の裁許や明治時代の話し合いにより、用水の配分がそれぞれ決められていました。
|

神流川八堰図(埼玉県立文書館 目で見る
埼玉の開発 より) |
しかし渇水になると、他の堰よりも少しでも多く自分の水田に水を引こうと、勝手に新たな堀を造ったり広げたり、時には岩盤に穴を空けたりする人がでて、「水争い」が起こりました。
「我田引水」ということわざは、こうした「水争い」を語源としています。さらに、神流川は上野国(群馬県)と武蔵国(埼玉県)の境を流れていることも、問題をより複雑にしていました。
この「水争い」は神流川の水瓶である下久保ダムが完成する昭和44年まで続きました。雨が降らない日が続いても、下久保ダムに貯えておいた水を流すことによって、神流川の水量が安定するようになり、神流川からは「水争い」がなくなったのです。 |
| ■サイトご利用にあたって |
 |
【独立行政法人水資源機構 利根川上流総合管理所 下久保ダム管理所】
〒367-0313 埼玉県児玉郡神川町大字矢納1356-3
TEL:0274-52-2746(代) FAX:0274-52-5408
http://www.water.go.jp/kanto/simokubo/ |








