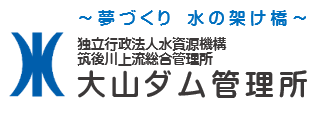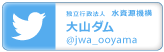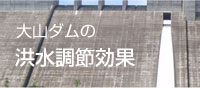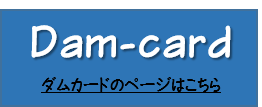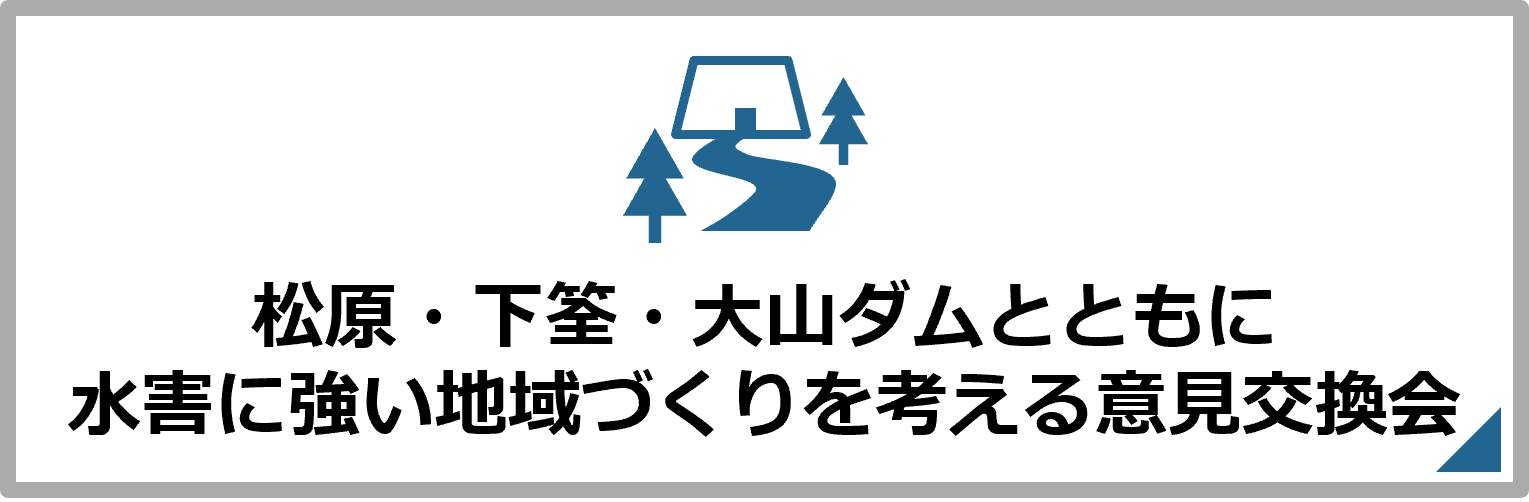筑後川上流総合管理所大山ダム管理所
〒877-0201 大分県日田市大山町西大山2008-1
TEL:0973-52-2445 FAX:0973-52-2446
E-Mail:oyama-d2@hita-net.jp
〒877-0201 大分県日田市大山町西大山2008-1
TEL:0973-52-2445 FAX:0973-52-2446
E-Mail:oyama-d2@hita-net.jp
大山ダムについて
![]() 流域の特徴
流域の特徴
![]() 洪水と渇水の歴史
洪水と渇水の歴史
![]() 大山ダムの目的を知る
大山ダムの目的を知る
![]() 大山ダムの特徴を知る
大山ダムの特徴を知る
筑後川は熊本、大分、福岡、佐賀の4県にまたがる九州第一の河川で筑紫次郎の愛称で呼び親しまれてきました。古くから、かんがい、舟運、発電などにより地域経済に寄与してきました。反面、一度豪雨に見舞われると、川はその様相を一変して暴れ狂い、数々の水害をもたらしてきました。
筑後川は流域面積2,860km2、幹線流路延長143kmの一級河川です。熊本県阿蘇郡南小国町を源として阿蘇外輪山や小国盆地の降雨を集め、日田市において玖珠川と合流し、その後多くの支川を集めながら筑後・佐賀両平野を貫流して有明海に注いでいます。
筑後川流域の年間平均降水量は約2,050mmであり、その約40%が6月から7月にかけての梅雨期に集中しています。台風期の8月から9月を含めると雨量は約60%に達します。日本の年平均雨量の約1,700mmと比較すると、350mm多く、山間部では3,000mmを超えるところがあります。
筑後川流域の産業については、特に、上流部ではスギ、ヒノキ等の人工林による林業が盛んで、日田市では木材品製造業が発達しています。中流では食料品製造業が盛んで、朝倉市、鳥栖市等に代表されます。次いでゴム製造業が久留米市、鳥栖市に発達しています。下流の大川市では、木材品製造業が発達しています。河口部付近の有明海ではノリ業が盛んで、その収穫量は全国の約3割を占めています。
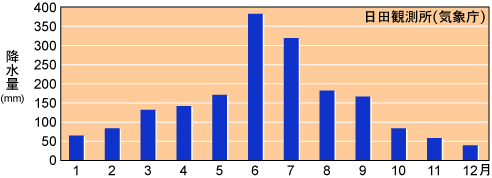
日田平均月別降水雨量(昭和46年から平成12年の30年間の平均値)
| 順 位 |
河川名 | 流域面積 (km2) |
幹線延長 (km) |
順 位 |
河川名 | 流域面積 (km2) |
幹線延長 (km) |
| 1 | 利根川 | 16,840 | 322 | 12 | 天竜川 | 5,090 | 213 |
| 2 | 石狩川 | 14,330 | 268 | 13 | 雄物川 | 4,711 | 133 |
| 3 | 信濃川 | 11,900 | 367 | 14 | 米代川 | 4,100 | 136 |
| 4 | 北上川 | 10,150 | 249 | 15 | 富士川 | 3,990 | 128 |
| 5 | 木曽川 | 9,100 | 227 | 16 | 江の川 | 3,870 | 94 |
| 6 | 十勝川 | 9,010 | 156 | 17 | 吉野川 | 3,750 | 94 |
| 7 | 淀川 | 8,240 | 75 | 18 | 那珂川 | 3,270 | 50 |
| 8 | 阿賀野川 | 7,710 | 210 | 19 | 荒川 | 2,940 | 73 |
| 9 | 最上川 | 7,040 | 229 | 20 | 九頭竜川 | 2,930 | 116 |
| 10 | 天塩川 | 5,590 | 256 | 21 | 筑後川 | 2,860 | 143 |
| 11 | 阿武隈川 | 5,400 | 239 | 22 | 神通川 | 2,720 | 120 |
| 順 位 |
河川名 | 流域面積 (km2) |
幹線延長 (km) |
| 1 | 筑後川 | 2,860 | 143 |
| 2 | 大淀川 | 2,230 | 107 |
| 3 | 球磨川 | 1,880 | 115 |
| 4 | 五ヶ瀬川 | 1,820 | 106 |
| 5 | 川内川 | 1,600 | 137 |
| 6 | 大野川 | 1,465 | 107 |
| 7 | 緑川 | 1,100 | 76 |
| 8 | 遠賀川 | 1,026 | 61 |
| 9 | 菊池川 | 996 | 71 |
| 10 | 大分川 | 650 | 55 |
| 11 | 矢部川 | 647 | 61 |