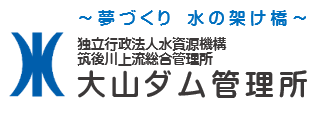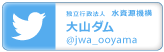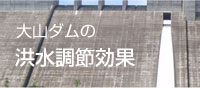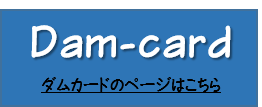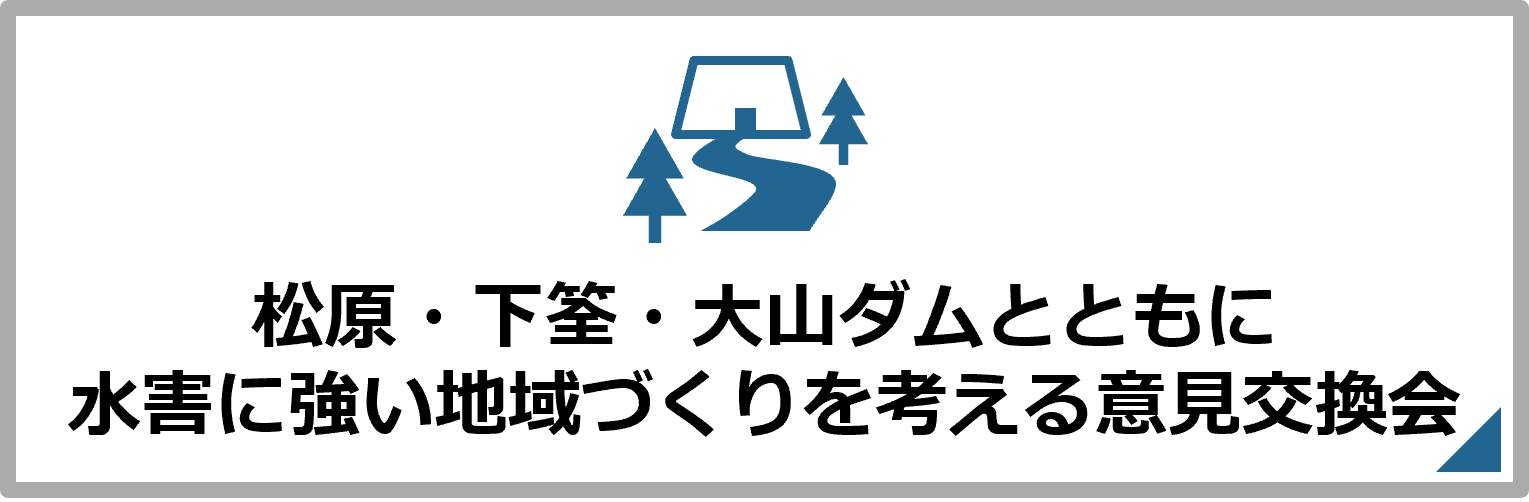筑後川上流総合管理所大山ダム管理所
〒877-0201 大分県日田市大山町西大山2008-1
TEL:0973-52-2445 FAX:0973-52-2446
E-Mail:oyama-d2@hita-net.jp
〒877-0201 大分県日田市大山町西大山2008-1
TEL:0973-52-2445 FAX:0973-52-2446
E-Mail:oyama-d2@hita-net.jp
大山ダムについて
![]() 流域の特徴
流域の特徴
![]() 洪水と渇水の歴史
洪水と渇水の歴史
![]() 大山ダムの目的を知る
大山ダムの目的を知る
![]() 大山ダムの特徴を知る
大山ダムの特徴を知る
洪水調節
筑後川では、150年に1回発生する規模の洪水を対象に治水計画が定められています。基準地点荒瀬において、基本高水のピーク流量10,000m3/sのうち、大山ダム等の洪水調節施設で4,000m3/sの洪水調節を行い、河道で6,000m3/sを処理する計画となっています。
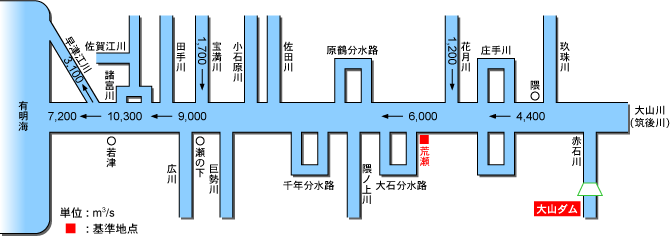
筑後川計画高水流量配分図
大山ダムの建設される地点においては、100年に1回発生する規模の洪水を対象に計画高水流量を690m3/sとしています。このうち、ダムにより570m3/sの洪水調節を行い、ダム下流の赤石川及び筑後川本川沿岸の洪水被害の軽減を図ります。
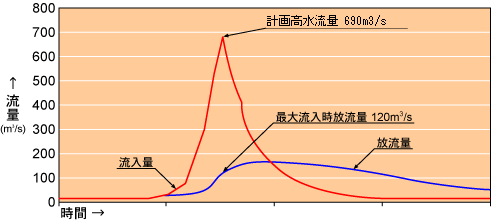
大山ダム洪水調節図
既得取水の安定化・河川環境の保全
良好な河川環境を維持し、歴史的に利用されてきた取水を安定させるために、必要に応じて大山ダムで貯めた水を放流します。
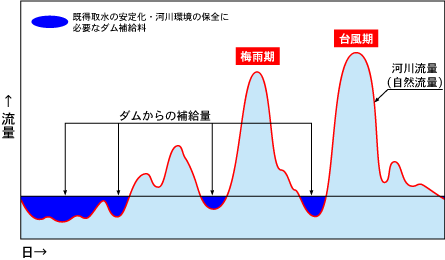
ダム補給による効果(模式図)
新規利水
大山ダムは久留米市瀬の下地点において、水道用水として新たに1.31m3/sを開発し、福岡県南広域水道企業団で0.707m3/s、福岡地区水道企業団で0.603m3/sの取水を可能とします。
ちなみに1.31m3/sは、1人1日の水使用量を350リットルとすると、約32万人分に相当します。
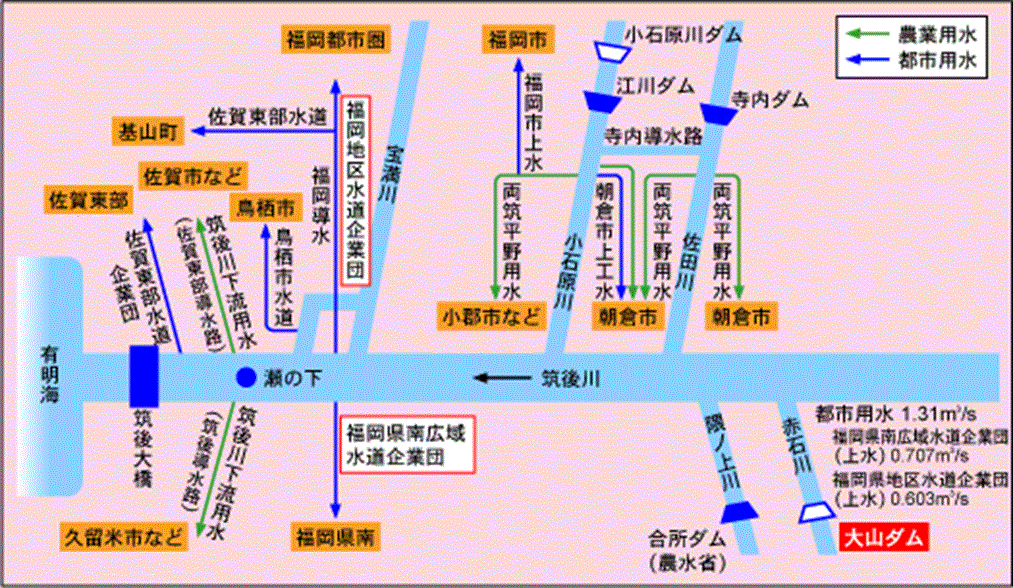
筑後川の開発現状況