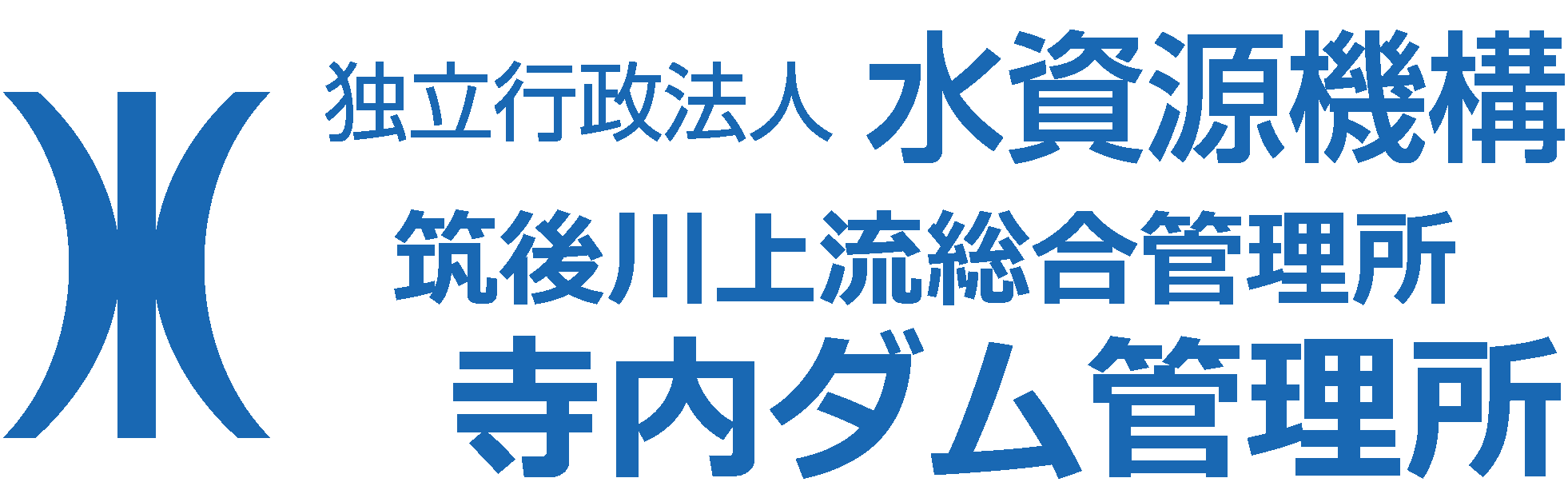寺内ダムの環境について
河川やダムなどの水辺周辺にすむ植物や動物を対象に、その種類などを調査するものです。この調査の結果は、河川やダムで工事や管理をしたりする時に、そこにすむ生き物たちのことを考えるための大事な資料になります。美奈宜湖(寺内ダム)では1992年度から行っています。
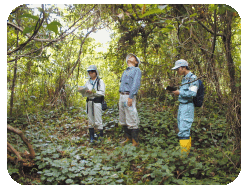
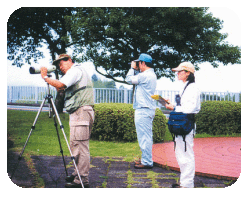



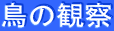
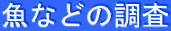
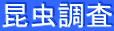
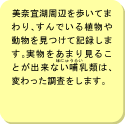
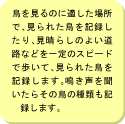
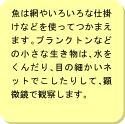
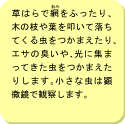
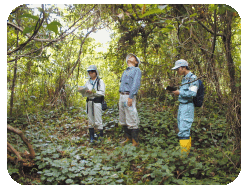
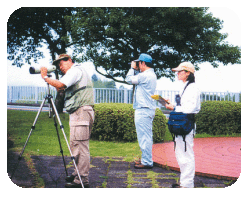


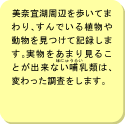
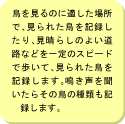
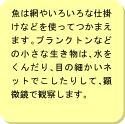
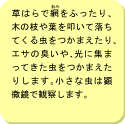
美奈宜湖にいる生き物は下の表の通りです。
| 生物種数と重要種の一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 項目 | 確認種数 | 重要種 | 調査年 | |
| 魚類 | 34 | 12 | H8~H24 | ||
| 底生動物 | 316 | 5 | H7~H25 | ||
| 植物 | 1,062 | 22 | H5~H23 | ||
| 鳥類 | 94 | 13 | H6~H15 | ||
| 哺乳類 | 44 | 12 | H6~H16 | ||
| 両生類 | |||||
| 爬虫類 | |||||
| 昆虫類等 | 2,290 | 17 | H5~H22 | ||
| 合計 | 3,840種(うち、重要種81種) | ||||
| 河川水辺の国勢調査により、美奈宜湖周辺には、たくさんの生き物がすんでいることがわかりました。特に昆虫は2,290種、植物は1,062種、鳥類は94種確認しました。 また、その中には稀少な種類もいることがわかりました。 みんなで力を合わせて環境を守っていきましょう。 |
||
| 生き物はみんな「食べたり、食べられたり」の関係の中で生きています。そのようなつながりを「生態系」と呼んだりします。では、この生態系の頂点に立つ最も強い生き物は何でしょう。 「植物」は「草食動物」に食べられ、「草食動物」は「肉食動物」に食べられます。さらにその「肉食動物」を食べる「肉食動物」もいます。 美奈宜湖周辺にすむ生き物を調べた結果、水辺から森にかけては、ミサゴ、トビなどのタカ類や、イタチがその頂点となると考えられます。 |
||
 |
ミサゴ 顔が白く、背と翼は上側が黒っぽく下側は白い。湖や大きな川で、魚をとって食べている。 |
|
| いつも恐いイメージがあり、なににでもおそいかかっていきそうなヘビ。でも、ヘビが食べる生き物もいれば、ヘビを食べる生き物もいるのです。また、こどものヘビは案外弱く、大人になればエサにするネズミにも食べられてしまいます。 ヘビだけをとってみても、いろんな生き物とのかかわりの中で生きているのですね。 |
||
| もともと日本にいなかったのに、人の活動(牧草や野菜といった農作物・ペット・荷物へのまぎれこみなど)によって外国から入ってきた生き物のことを「外来種」と呼びます。これに対してもともとその場所にいる生き物を在来種といいます。 | 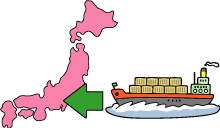 |
|||||||||||||||||||
| 外来種は意外と身近にたくさんいます。たとえば四ッ葉のクローバーでおなじみのシロツメクサは、牧草として外国からやってきました。また、アメリカザリガニも外来種です。日本にはわかっているだけでも約2,000種もいます。 | 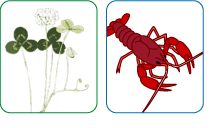 シロツメクサ アメリカザリガニ |
|||||||||||||||||||
| 国では外来種の被害を防止するために「外来生物法」という法律を作りました。また、国民ひとりひとりが守るべきこととして「外来生物被害予防三原則」を提言しています。 | ||||||||||||||||||||
| 1. 入れない | 2. 捨てない | 3. 拡げない |
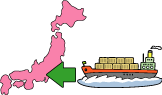 |
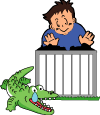 |
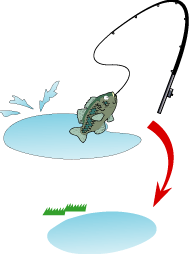 |
| ・外来種をむやみに日本に入れない | ・ペットを捨てない | ・野外にいる外来種をつかまえて他の場所に放さない |
美奈宜湖周辺には日本や福岡県でも、最近少なくなってしまった種類や、めずらしい種類の生き物がまだまだいて、「重要種」などと呼ばれています。このホームページ上にも沢山出てくるので、しっかりチェックしてね!
希少種の多くは、すみかがつぶされたり、汚されたり、むやみに狩られたりして、数が減ってきています。昔は日本にもニホンオオカミなどがいたのに、今はいなくなってしまいました。そのようなことをくり返さないためにも、環境や自然に目をむけて生き物のことを理解し、めずらしさで捕まえるのはよしましょう。
 ミサゴ |
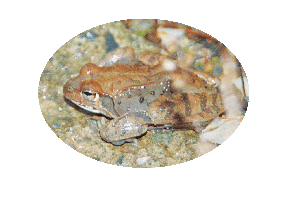 ヤマアカガエル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 寺内ダム管理所
〒838-0029 福岡県朝倉市荷原1516-6 Tel 0946-22-6713(代表)
ご意見・ご感想はこちらへどうぞ sakura123@lion.ocn.ne.jp
Copyright © 寺内ダム管理所.