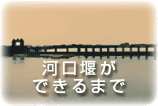潮止め樋門の設置と河口堰の建設
潮止め樋門の設置
旧吉野川・今切川流域では、16世紀末より新田開発が行われてきましたが、旧吉野川・今切川の流路の大半が感潮部にあるため、土壌の塩害が深刻な地域でした。
干ばつにより両河川の水量が少なくなると、川の流れによって海水の遡上を抑えることができなくなり、農業用水の取水が不可能となっていました。
従来より干ばつ時には、旧吉野川の今切川分派地点(三ツ合堰)下流で水争いが繰り返され、特に1930年(昭和5年)の大干ばつの際には、三ツ合堰に石材が投げ入れられたり、農民が大挙して徳島県庁に押し掛けたりするなど騒然とした状況になりました。
これを契機にして、両河川に潮止め樋門を設置する以外に水争いの解決手段はないとして、両河川で県営事業としての潮止め樋門建設工事が開始されました。
今切川潮止め樋門は1936年(昭和11年)に完成し、旧吉野川潮止め樋門については、途中戦争による工事中断をはさんで1949年(昭和24年)に完成しました。
 今切川潮止樋門 (今切川ダム) ※クリックで当時と現在の写真 |
 旧吉野川潮止樋門 (松茂ダム) ※クリックで当時と現在の写真 |
河口堰の建設へ
2つの潮止め樋門の完成により樋門上流側の湛水域が淡水化され、農業生産性は向上しました。
しかし、1946年(昭和21年)の南海地震やその後の余震の影響により、地盤沈下や基礎部分の破損により潮止め機能が低下し、途中改良工事を行いましたが、老朽化も進み十分な機能回復はできませんでした。
こうした状況のなかで、早明浦ダムの建設等を内容とした「吉野川水系における水資源開発基本計画」(フルプラン)が1967年(昭和42年)閣議決定されました。
フルプランの中で、2つの潮止め樋門に替わる現在の旧吉野川河口堰・今切川河口堰の建設が「旧吉野川河口堰事業」として位置づけられました。
フルプランに基づき、1971年(昭和46年)に今切川河口堰、1973年(昭和48年)に旧吉野川河口堰の建設に着手し、1974年(昭和49年)に今切川河口堰が、1975年(昭和50年)に旧吉野川河口堰が完成しました。
| 1936年(昭和11年) | 今切川潮止樋門完成(徳島県) |
|---|---|
| 1949年(昭和24年) | 旧吉野川潮止樋門完成(徳島県) |
| 1951年(昭和26年) | 農林省岡山農地事務局が、旧吉野川流域の農業水利の現況調査開始 |
| 1954年(昭和29年) | 農林省岡山農地事務局が、吉野川下流部の農業水利の実態、第十堰の漏水調査等について調査開始(35年に成果発表) |
| 1964年(昭和39年) | 徳島県が旧吉野川河口堰改修計画調査開始 |
| 1968年(昭和43年) | 建設省(現 国土交通省)が旧吉野川河口堰建設事業計画をまとめる |
| 1970年(昭和45年) | 「吉野川水系における水資源開発基本計画の一部変更」閣議決定。「旧吉野川河口堰建設事業に関する事業実施方針」指示。 「旧吉野川河口堰建設事業に関する事業実施計画」認可 |
| 1971年(昭和46年) | 今切川河口堰本体工事着工 |
| 1973年(昭和48年) | 旧吉野川河口堰本体工事着工 |
| 1974年(昭和49年) | 今切川河口堰竣工 |
| 1975年(昭和50年) | 旧吉野川河口堰竣工 |
| 1976年(昭和51年) | 旧吉野川河口堰管理所発足 |
| 2003年(平成15年) | 水資源開発公団から独立行政法人水資源機構へ移行 |