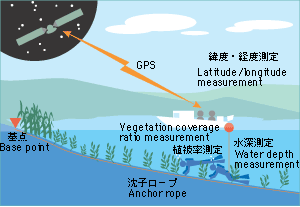
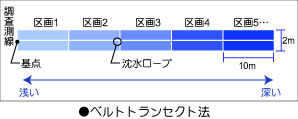 |
湖岸に設定した基点から沖に向けて沈水植物生育下限まで沈子ロープを設置し、GPS(衛星航法装置)を用いて約100m(1997年は約220m)ごとに緯度・経度を測定した。沈子ロープに沿って、10mごとに水深と埋没深を測定しました。また、ベルトトランセクト法により、観察幅2mで測線上を10mごとに底質類型の占有度、沈水植物の植被率、種別被度階級を観察し、記録しました。
なお、観察は沈水植物生育下限を確認するまで行い、南湖の遠浅の測線では最大2,000mまでとしました。
音響測深器を測線に沿って走査し、100〜200mごとにマークを入れ、記録紙から10mごとに水深と群落高を0.1mまで読み取りました(ただし、1997年と1998年は観測していません)。
|